

お問合せの電話番号はこちら06-7506-3993

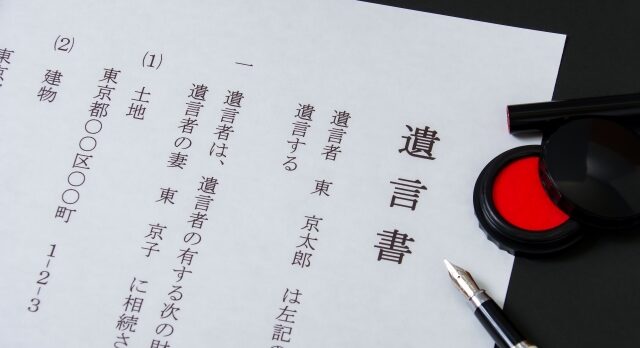
行政書士がサポートする遺言作成
遺言の作成は行政書士などの専門家に相談することで確実かつ安心に進められます。
遺言は、自分の最期の意思を法的に残す重要な手段です。
しかし、書き方や法的ルールが複雑で間違えると無効になることもあります。
だからこそ、遺言作成は専門家である行政書士に相談するのが安心です。
行政書士は法律の専門知識を持ちつつ、親身にあなたの意向に沿った遺言作成をサポートします。
この記事では、行政書士が行う遺言作成について、確実に想いを残すためにできることをテーマにわかりやすく解説します。

「遺言書は自分で書けばいい」と考える人が多いですが、実は注意が必要です。
実は、遺言書は厳格な法律ルールがあります。
例えば、自筆証書遺言の場合、全文を自分で手書きしなければならず、日付や署名も厳密な形式を守る必要があります。
これを怠ると遺言は無効になり、結果的に相続トラブルが起きてしまうこともあります。
さらに、遺言の内容があいまいだったり、法的に不適切だったりすると、遺言執行がスムーズに行かず家族が困るケースもあり、加えて、遺言書の保管方法や検認手続きの知識も必要です。
こうした複雑さから、遺言作成で悩む方や不安を抱える方は少なくありません。

あなたも自分にもしものことがあったときに、残された家族が争わないように遺言を残した方がよいと思っているのではないでしょうか。
そして、次のような不安を抱えているのでは?
こうした声はよく聞かれます。
特に初めて遺言を作る方にとっては、専門用語や法的手続きは難解です。
身近な相談相手がいないと、一人で悩みを抱え込んでしまいがちです。
だからこそ、遺言作成は行政書士などの専門家と一緒に進めることで安心できます。
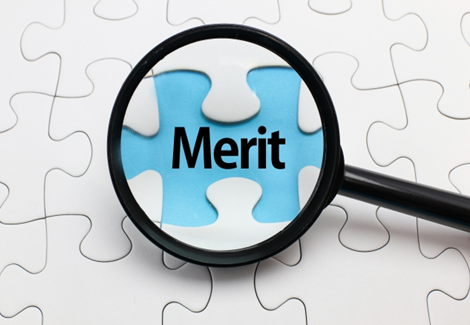
行政書士は法律の専門知識を持ち、遺言書の作成や法的チェック、保管サポートまで幅広く対応可能です。
具体的には以下のメリットがあります。
行政書士は、民法に基づく遺言書の形式や内容に精通しており、法的効力を持つ遺言書の作成をサポートします。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言(実務的には少ない)など、依頼者の希望に応じた適切な形式を選択し、必要な手続きを案内します。
もっとも危惧される遺言書が無効とされるリスクを最小限に抑え、遺産分割時のトラブルを防ぐことができます。
行政書士は、依頼者の家族構成や財産状況を考慮し、最適な遺言内容を提案します。
例えば、特定の相続人に対する遺贈、遺産分割方法、遺留分の配慮など、個別の事情に応じたアドバイスを行います。
これらを適切に行うことで、遺言書が依頼者の意向を正確に反映し、相続人間の不和を防ぐことができます。
遺言書の保管方法や、遺言者の死亡後に必要な検認手続きについても、行政書士は適切なアドバイスを提供します。
公正証書遺言の場合は公証役場での保管が行われますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です。
これらの手続きを円滑に進めるためのサポートを行い、遺言の効力を確保します。
行政書士は、遺言書の作成だけでなく、相続時に発生しやすいトラブルを未然に防ぐためのアドバイスも行います。
例えば、遺留分の侵害を避けるための配慮、特定の相続人への負担軽減策、遺産分割協議の進め方など、実務的な視点からの助言を提供します。
このことより相続後の紛争を最小限に抑えることができます。
ただし、遺言書作成が訴訟に発展する可能性が高い場合や、具体的な裁判対応が必要なケースについては、行政書士の業務範囲外となるため、弁護士への相談が推奨されます。
行政書士は裁判所での手続き代行はできませんが、遺言書の作成支援や遺産分割協議のサポートは得意分野です。

当事務所では行政書士が行う遺言に関するサポートを以下の内容で提供しています。
まずは無料相談で、現在のお悩み・ご家族構成・主な財産の内容・想定される相続関係を丁寧にヒアリングします。
遺言書は「ただ書けば安心」ではなく、目的や優先順位の整理が肝心です。
当事務所では、誰に何を、どの方法で遺すのがよいか、税務や家族関係のリスクも踏まえて分かりやすくご説明します。
必要な書類やおおまかなスケジュール、費用の目安もこの段階で明示します。
「自筆・公正証書のどちらが良いの?」「家族信託との違いは?」などのご質問にも率直に回答し、最初の一歩の不安を解きほぐします。
遺言書の形式は一見シンプルですが、文言や記載順、付言事項の使い方によって伝わり方が大きく変わります。
当事務所は、配偶者・子・再婚・事業承継・障がいのあるご家族がいる場合など、個別事情に応じた書き方を具体例でアドバイスを行います。
特定の不動産・預貯金・株式の指定方法、予備的な受遺者の定め、遺留分への配慮、相続人間の公平感を保つ工夫も提案します。
将来の手続きが滞らないよう、地番・口座情報の整理方法や、保険・ローン・共有名義の注意点まで、実務目線でサポートします。
ご希望に応じて、ヒアリング内容をもとに当事務所が遺言書の文案を起案し、推敲・確定まで伴走します。
自筆証書を選ぶ場合は、法定の方式(全文・日付・署名押印等)を満たすための具体的な書き方・清書手順をアドバイスいたします。。
誤記・解釈のぶれ・特定不能を招く表現を徹底的にチェックし、将来の紛争リスクを抑えます。
既に作成済みの遺言がある方には、最新の家族状況や資産構成に照らした見直し診断も実施いたします。
必要に応じて訂正・付言・遺言執行者条項の追加をご提案します。
完成した遺言は保管が重要です。
自筆証書の場合は法務局保管制度の活用や、封筒・目録・保管場所の分散管理等の実務的な工夫をお伝えします。
公正証書遺言をご希望の方には、公証人との事前折衝、必要書類の収集、当日の立会調整まで一括でサポートを行います。
証人手配が必要な場合もご相談ください。
作成後の正本・謄本の扱い、変更・撤回時の流れ、住所氏名変更があった場合の対応など、作った後に困らない運用方法まで具体的にご案内します。
遺言は「正しく実行されてこそ効果」を発揮します。
遺言執行者の指定は、相続人間の負担軽減と迅速な名義変更に有効です。
当事務所は、親族・専門職のどちらを指定すべきか、複数指定・予備指定・報酬条項の書き方を含めてご提案します。
特別受益や寄与分への配慮、死後事務やデジタル遺産の取扱い、相続開始後の連絡体制づくりも併せて設計します。
※訴訟等の法的紛争が想定される事案では、弁護士の関与が必要となるため、適切に連携・ご紹介いたします。
自身も相続を経験した立場として、あなたの「安心できる遺言作成」を全力で支援します。
遺言作成は、以下のような不安や悩みを抱えている方を対象としています。
「誰に何をどれだけ渡すか」を明確にし、解釈の余地をできる限り排した遺言は、最も効果的な争族対策です。
ご家族の関係性や希望を丁寧にヒアリングし、遺留分や公平感への配慮、代償金や予備的受遺者の定めなど、感情面・実務面の両面から火種を減らす設計が必須です。
また、付言事項で想いも言語化し、残される方が納得しやすい形に整えます。
※「付言」とは、遺言書に法的効力を持たせる部分(法定遺言事項)とは別に、遺言者の想いやメッセージを書き記す部分のことです。
法的効力はありませんが、遺言者の気持ちを相続人に伝える大切な手段として活用されます
「形式の不備が怖い」「公正証書が安全と聞くが流れが分からない」――こうした不安は当然です。
私たちは、自筆・公正証書それぞれのメリットや費用感、必要書類、当日の段取りまで具体的にご説明し、文言のテンプレではなく、あなたの事情に即した条項へと落とし込みます。
清書の方法、押印・日付・訂正のルール、保管のコツまで一緒に確認し、確実に残せる状態にします。
不動産の特定(地番・家屋番号)、口座や有価証券の表示、共有持分や予備条項など、つまずきやすいポイントは多岐にわたります。
誤解や特定不能を招く表現を避け、将来の手続が止まらない実務的な文案を作成・推敲しますし、すでに下書きがある方のチェックや、見直しアドバイスのみのご依頼も歓迎です。
清書手順やチェックリストもお渡しし、安心して署名・押印できるよう伴走します。
特別受益・寄与分、再婚家族、同居と別居の不公平感、事業や収益不動産の承継などの争点は事前の設計で大きく減らせます。
遺留分への配慮、代償金の設定、役割分担を明記する付言事項、遺言執行者の指定など、起こりがちな争いを具体的に想定した条項をそれぞれ置かれた環境に合わせて整理していきます。
デジタル遺産や死後事務の取り決めも含め、手続の停滞と感情的対立を回避する実行力のある遺言を作ります。
作るだけでなく「きちんと保管し、スムーズに実行する」までが大切です。
自筆の法務局保管制度の活用、公正証書の作成サポート(公証人との調整・証人手配)、正本・謄本の管理、住所変更等のアフター対応、相続開始後の名義変更手続や遺言執行者受任まで一貫支援が必要です。
状況変化に応じた見直しや追加条項の提案も行い、長期的に困らない仕組みを作ることが肝要です。
行政書士に相談することで、より確実で安心できる遺言が実現します。