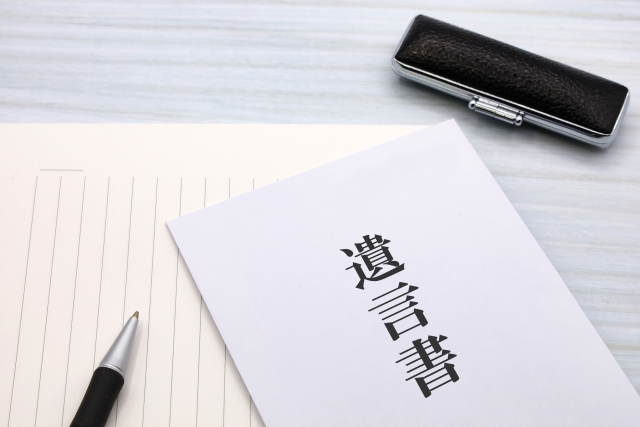
「遺言」と聞くと、「まだ自分には早い」と感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、遺言は年齢に関係なく、誰にでも関係のある大切な意思表示の手段です。
私たちは日々の暮らしの中で、家族のこと、大切な人のことを想いながら、少しずつ築いてきた財産や人との関係性を持っています。それらを、自分の死後にどう託すかを考えることは、「自分らしい最期の迎え方」とも言えるでしょう。
また、遺言をきちんと残しておくことで、残された家族の間での争いを防ぎ、大切な人たちに安心と感謝を届けることができます。
以下に、遺言の基本的な種類や作成のポイントについてご紹介します。
遺言書の種類と特徴
遺言書には主に次の3種類があります。それぞれにメリット・注意点があるため、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
自筆証書遺言
全文を自筆で書く遺言書で、もっとも手軽に作成できます。2020年からは財産目録の部分をパソコンで作成しても良くなりました。
ただし、形式不備があると無効になる恐れがあるため、専門家に確認してもらうことをおすすめします。
2020年以降は、法務局での「自筆証書遺言の保管制度」もスタートしており、紛失や改ざんの心配も軽減されています。
公正証書遺言
公証人と証人2名の立会いのもとで作成する遺言です。内容が法的に整っており、家庭裁判所の検認も不要なため、安全性・確実性に優れています。
高齢で字を書くことが難しい方にも対応できる点が特徴です。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に「存在」だけを認証してもらう形式です。ただし、自筆証書遺言と同様に検認が必要で、あまり一般的ではありません。
遺言書に書ける内容とは
遺言書には主に以下のような内容を記載することができます。
財産の分け方(相続分の指定、特定の人への遺贈)
遺言執行者の指定
認知(婚外子の認知など)
相続人の廃除や取消し
特に、家族関係が複雑な場合や、特定の人に財産を残したい場合などは、遺言書を活用することでトラブル防止につながります。
遺言書作成時の注意点
財産の記載はできる限り具体的に:例)「○○銀行△△支店の普通預金 口座番号×××」など。
日付、署名、押印を忘れずに(特に自筆証書遺言)
相続人の気持ちにも配慮を:内容だけでなく、想いを伝える「付言事項」も検討してみましょう。
行政書士に依頼するメリット
✔ 法的に有効な遺言書の作成サポート
形式不備のない遺言書を作成することで、将来のトラブルを防止します。
✔ 想いを形にするサポート
法律だけでなく、依頼者の「気持ち」や「意志」も大切にしながら文案を作成します。
✔ 公証人との連携による公正証書遺言の作成も対応
事前準備から当日の立会いまで、しっかりサポートいたします。
✔ 家族信託や相続対策との連携
将来の相続に向けて、遺言だけでなく家族信託などと組み合わせたご提案も可能です。
まとめ
遺言は、残された家族への「最後のラブレター」とも言われます。
トラブルを防ぐためだけでなく、大切な人に想いを伝えるためにも、ぜひ遺言書の作成を検討してみてください。
「いつか」のために、今からできることがあります。
相続に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。