家族信託は、相続や財産管理を円滑に進めるための仕組みとして注目を集めています。
特に認知症対策や円滑な資産承継に役立つため、多くのご家庭で検討されています。
しかし実務の現場では、「家族信託を導入したことで新たなトラブルが生じた」という相談も少なくありません。
例えば、兄弟間での不公平感、契約書の不備による金融機関対応の拒否、受託者の管理不備による不信感などです。
ただし、信頼できる専門家のサポートと、家族全員の合意形成を行えば、これらのトラブルの多くは未然に防げます。
この記事では、行政書士の立場から「よくある失敗例」と「予防のためのチェックリスト」をまとめて解説します。
家族信託に潜む代表的なトラブル
では、ここからよくあるトラブルについて解説していきます。
相続を巡る想定外の争い

家族信託は「相続トラブルを防ぐ仕組み」として注目されていますが、実際には設計や運用を誤ると、かえって家族間の不信感や争いの火種となるケースもあります。
ここでは、実際に起こりがちな3つのトラブル例を紹介します。
長男が受託者となり実権を持った結果、兄弟間に不公平感が生まれる
信頼できる家族として長男を受託者に選任したものの、「財産の運用方針」や「受益者への分配」を独断で進めてしまうケースがあります。
- 受益者(たとえば他の兄弟)に説明が不十分
- 収益や不動産の管理状況が不透明
- 信託口座の扱いが個人資産と混同してしまう
このような状況が続くと、「長男が勝手に財産を動かしているのではないか」と疑念が生まれ、結果として兄弟間で深刻な対立に発展します。
定期的に収支報告を行い、受益者全員が内容を確認できる体制を作ることが重要です。
ある相続人だけに有利な設計となり、他の相続人から不満が噴出
家族信託では、委託者(親)が「この子には多めに渡したい」などと考え、特定の相続人を優遇する設計にしてしまうことがあります。
しかし、その設計が他の相続人に不利に見える場合「不公平な信託だ」「遺留分の侵害ではないか」といった争いに発展します。
特に、遺留分(民法上の最低限の取り分)に配慮していない設計は、のちのち訴訟になるリスクもあります。
公平性を意識し、信託設計時に相続人全員の理解を得ておくことが大切です
「信託終了後の帰属先」を曖昧にしており、相続人同士で争いに発展
家族信託には「信託終了後、誰に財産を最終的に帰属させるか」という設計が必要です。
この部分があいまいなままだと、信託終了時に「結局この不動産は誰のもの?」という状態になります。
- 帰属権利者の指定がない
- 書面ではっきり書かれていない
- 信託契約と遺言の内容が矛盾している
このようなケースでは、最終的に家庭裁判所や弁護士を交えた調停に発展することも珍しくありません。
信託契約書の作成時点で、終了後の帰属先(次の受益者など)を明確にしておくこと。
契約内容の不備によるトラブル
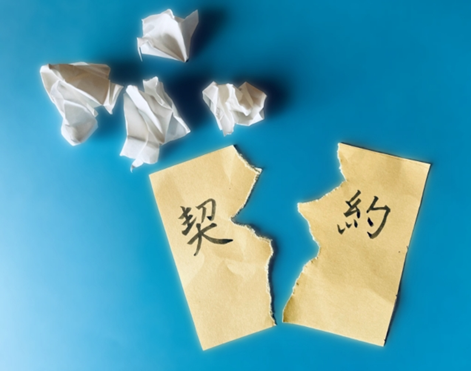
家族信託の契約書は、法律上の効力を持つ正式な「信託契約書」です。
しかし、内容が不明確だったり、実務運用を想定していなかったりすると、 せっかくの仕組みが機能せず、銀行や不動産の手続きでトラブルになることがあります。
契約書の表現が不明確で、銀行に口座開設を断られる
家族信託を開始しても、銀行口座を開設できなければ実際の運用ができません。
契約書の記載が曖昧だったり、信託財産や受託者の権限が明記されていないと、銀行から「この内容では信託口座は作れません」と断られるケースがあります。
- 契約書に信託財産の範囲が具体的に書かれていない
- 委託者・受託者・受益者の関係が不明確
- 銀行担当者が内容を読み取れない
各金融機関の実務運用を踏まえ、「信託財産の範囲」「受託者の権限」「信託目的」を具体的に明記しておくことが重要です。事前に銀行の信託口座対応状況を確認しておくのも効果的です。
信託終了後の財産行き先を定めておらず、裁判で決着せざるを得ない
信託契約には「信託終了時に誰へ財産を帰属させるか(帰属権利者)」を明記する必要があります。
これを記載し忘れる、あるいは曖昧な表現にしてしまうと、信託終了後に「最終的にこの財産は誰のものか」が不明となり、相続人間で争いが発生します。
実際、帰属先が不明確なために家庭裁判所での判断を仰ぐケースもあります。
契約書作成時に必ず「信託終了後の財産の帰属先」を明記すること。また、将来的に変更が想定される場合は、その変更手続きのルールも定めておくと安心です。
受託者が複数いるのに意思決定ルールを設けず、動けなくなる
家族信託では、信頼できる複数人を受託者に選ぶケースもあります。
しかし、契約書で「どのように意思決定を行うか(多数決なのか、全員一致なのか)」を定めていないと、意見が分かれた場合に何も決められなくなってしまいます。
- 不動産の売却をしたいが、一人が反対して進められない
- 銀行が全員の同意を求め、手続きが滞る
契約書に「受託者の意思決定ルール(過半数決定・代表者制など)」を明記する。また、代表受託者を1名定めておくと実務上スムーズです。
実務上の負担や誤解
受託者が会計処理を怠り、税務申告漏れで追徴課税を受ける
「家族信託で相続税が安くなる」と誤解して導入し、期待外れに
契約書を作成しただけで安心し、制度の見直しを怠る
こんなお悩みはありませんか?
「親が元気なうちに備えたいけど、成年後見は堅苦しそう」
「兄弟間で相続トラブルが起きないか心配」
「インターネットの情報はバラバラで、誰に相談すればいいか分からない」
「契約書を自作できると聞いたけど、失敗しないか不安」
こうした不安は多くの方が抱えており、放置すると後に大きなトラブルにつながる可能性があります。
トラブルを防ぐ3つのポイント
わかりやすくトラブルを防ぐ3つのポイントを挙げていきます
契約内容を明確にする
家族信託は「契約がすべて」です。財産の範囲、管理方法、終了後の帰属先まで具体的に明記する必要があります。曖昧な契約は必ず後の紛争の原因になります。
家族全員で合意形成を行う
「受託者と委託者だけ」で話を進めると、後から「聞いていない」と不満が出ます。
相続人候補全員に説明する
議事録を残し、透明性を確保する
専門家のサポートを得る
行政書士:契約書作成・制度設計
税理士:税務申告や会計処理
弁護士:将来的な紛争予防
複数の専門家と連携して進めることで、安全性が高まります。
行政書士による家族信託サポート
私は行政書士として、家族信託に関する以下のサポートを行っています。
初回相談で「家族信託が本当に必要か」を一緒に検討
実務で使える契約書を作成
銀行や不動産登記など、実務対応もフォロー
税理士・弁護士とのネットワークを活かした総合支援
家族信託が特に有効な方
認知症による口座凍結に備えたい方
相続トラブルを未然に防ぎたい方
成年後見制度に抵抗がある方
家族に迷惑をかけずに財産承継を進めたい方
家族信託トラブルは予防できる
家族信託は便利な制度だが、トラブルも多い
主な原因は「契約の不備」「合意不足」「誤解」
専門家と家族全員の協力でトラブルは防げる
家族信託は「準備の質」で成否が決まります。正しく備えることで、大切な家族の安心を守りましょう。


