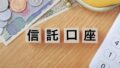家族信託は「使い方次第」で大きな味方になる制度です。
家族信託は、将来の認知症や相続の不安を軽減する有力な手段です。
しかし、メリットばかりではなく注意すべきデメリットも存在します。
この記事では、家族信託の本質とその活用法をわかりやすく解説し、ご自身やご家族の将来に備える第一歩として行政書士への相談をおすすめしています。
こんな悩みはありませんか?

私自身も還暦近くになったころから親の介護問題が深刻化してきました。
そして、そんな親を見ていると、自分が親の年齢に近くなった時に、家族(息子)を同じ境遇にさせることになると強く感じました。
具体的には以下のような不安材料を抱えております。
それぞれ解説していきます。
将来、認知症になったら自分の財産はどうなる?

これは、親が認知症になった場合に、その財産がどうなるのかということでもあります。
銀行口座が凍結されるリスク

もし判断能力が低下したとき、銀行口座が凍結されると、子どもでも引き出すことができません。
普通預金でも、キャッシュカードを使えば、問題はないと思われるかもしれませんが、例えば、カードが損傷して作り直す場合や、定期預金であれば、本人が解約をするために、銀行に出向く必要もあります。
子供に委任をしたとしても、親にかならず銀行から確認が入ります。
その時に、「解約する気はないし、何の話がわからない」と言われてしまえば、もう解約することができなくなる可能性が高いです。
※ そもそも口座が凍結されてしまうと後見人を選任する等の手続きがないと引き出しはできません。
不動産の売却や修繕ができない
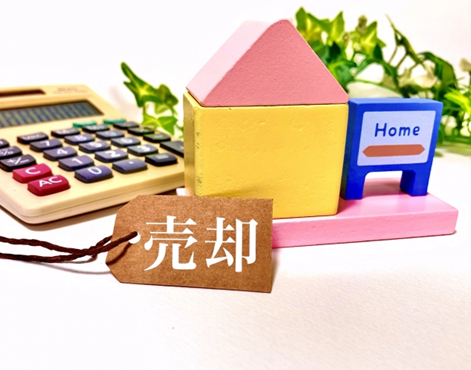
認知症発症後は、不動産の管理や売却が困難になり、空き家リスクや維持費の負担が増加します。
親の財産管理が心配。兄弟で意見が食い違いそう…
私が父を亡くした際は、幸運にも兄弟姉妹間でうまく話しがまとまったので、トラブルに至りませんでした。
ただ、周りの話を聞いていると、兄弟と疎遠になっているケースや考え方の相違もあり、話し合いがスムーズにいかないことも起こりえます。
親の意思がわからずトラブルに…
日頃から家族が集まる機会が多い場合でも、やはりお金のことはデリケートな問題なので、なかなか話題にしずらいですね。
相続時に「親はこう言っていた」など、言った言わないで兄弟間で揉めるケースが少なくありません。
認知症発症後では手遅れになる場合も…
これは実際に知人のケースなのでが、ご両親は健在ではあるものの、お父様がすでに認知症で施設に入っており、お母様は大病を患っておられます。
もともとお父様名義で自宅があるものの、お父様が認知症のため、売却や大きな改修はできません。
そんな時には成年後見制度を利用する方法はありますが、この制度は柔軟性が低く、自由な財産管理には向きません。
実際に多くの方が不安を感じています

「最近、母の物忘れが増えてきて心配…」
「父のアパート経営を手伝っているが、将来のことを考えると不安」
「今は軽い物忘れ程度だが、もっとひどくなったら預金もおろせない?」
これらは行政書士等が相談を受けた内容の一例です。
高齢化社会が進む中、65歳以上の高齢者の約7人に1人が認知症になると言われています(厚生労働省調査)。
誰にとっても「他人ごとではない問題」なのです。
家族信託がその悩みを解決できるかもしれません

これまで話をしてきた悩みを解決する手段の一つが「家族信託」です。
家族信託は、信頼できる家族に財産の管理・運用・処分を託す制度です。
信託契約を結ぶことで、元気なうちに将来に備えることが可能になります。

家族信託のメリットとデメリット
どんな制度でもメリットとデメリットが必ずあります。
利用する際には、しっかりとメリットデメリットを把握しておくことが重要です。
家族信託のメリットについて

具体的に、家族信託のメリットについて解説していきます。
柔軟な財産管理ができる
家族信託を活用すれば、将来ご本人が認知症などで判断能力を失ってしまった場合でも、信頼できる家族(受託者)があらかじめ定められたルールに従って、財産を適切に管理・活用することが可能になります。
例を挙げると、ご本人が収益のある不動産を持っていた場合に、家賃を管理しつつ、また必要な修繕を行うこともできます。
また、ご本人の生活費や医療費にあてるために預貯金を引き出して使ったりと、状況に応じた柔軟な対応が可能になります。
そして、成年後見制度のように家庭裁判所の監督や報告義務が必要でないので、より自由度の高い財産管理ができるのも特徴です。
ご本人の希望やご家族の事情に応じて、実情に合った資産運用が可能になります。
※ もちろん、成年後見制度を利用するメリットもあるので、利用される本人の環境によります。
成年後見制度より自由度が高い
成年後見制度は「守る」制度ですが、家族信託は「活かす」制度です。
つまり成年後見制度は、判断能力が低下した本人の財産を「保護する」ための制度です。
家庭裁判所の監督のもと、後見人が本人の利益を守ることを第一に行うため、日常生活に必要な支出以外の財産の処分や運用には慎重さが求められ、柔軟な財産活用には一定の制約がある場合があります。
一方、家族信託は、本人が元気なうちに自らの意思で信頼できる家族に財産の管理・運用・処分の権限を託す制度です。
信託契約であらかじめ取り決めた内容に沿って、本人の希望やライフプランに沿った形で財産を「積極的に活かす」ことが可能になります。
たとえば、不動産の活用や資産の組み替え、子世代への承継まで含めた柔軟な設計ができる点が特徴です。
ただし、成年後見制度と家族信託は、対立する制度ではなく、目的や状況に応じて使い分けるべきものです。
家族信託では対応しきれない身上監護(介護や医療に関する意思決定など)の場面では、後見制度の活用が重要になります。
したがって、家族信託は成年後見制度の代替ではなく、選択肢の一つとして、より本人の意向を実現しやすい制度設計を目指すための「補完的な制度」として位置づけることができます。
相続トラブルを未然に防げる
家族信託を活用する場合、親がまだ元気なうち(判断能力を維持している間)に自分の財産の管理や承継方法について、具体的な取り決めを信託契約という形で明文化できます。
このことにより、相続が発生した際に「誰にどの財産を渡すか」「どのように活用するか」といった親の意思がはっきりと示されるため、後々に兄弟間で争いが起こるリスクを大きく減らせます。
また、家族信託は契約の内容に基づき受託者が財産管理を行うため、遺産分割協議の必要がないケースも多く、スムーズに資産を承継することが可能になります。
特に、不動産など換金が難しい財産の扱いや、介護費用の支払いなども事前に取り決めしておけるため、相続後の混乱や誤解を防ぐ役割も果たします。
このように、家族信託は「親の想いを形にし、家族全員が納得できる仕組み」を作ることで、相続トラブルを未然に防ぐ強力な手段となります。
二次相続まで指定できる
自分の死後だけでなく、その次の世代まで財産の流れを決められます。
一次相続:親が亡くなったときに、配偶者や子どもが財産を引き継ぐこと
二次相続:一次相続で配偶者が財産を受け取った後、その配偶者が亡くなったときに、子どもなどが受け継ぐこと
家族信託のデメリットについて
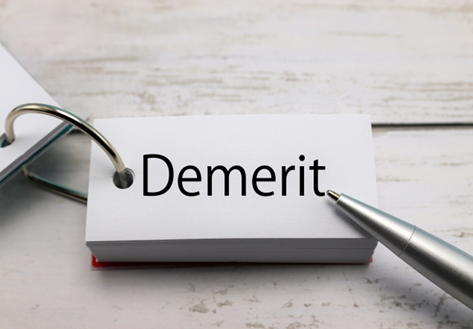
次に、家族信託のメリットについて解説していきます。
手続きが複雑で専門家のサポートが必要
家族信託は自由度の高い仕組みですが反面、その契約内容によっては複雑になりがちです。
契約書は当事者間の意思を正確に反することはもちろんですが、法律上も有効な内容で作成しなければなりません。
たとえば、信託財産の範囲、受託者の権限、受益者の変更や信託の終了時期などを曖昧に記載してしまうと、後々「誰が何を決める権利があるのか」「財産を誰に引き継ぐのか」といった点でトラブルが発生する可能性があります。
さらに、形式的には信託契約書が整っていても、税務面での誤解や不備があると、贈与税や所得税など思わぬ課税を受けることもあります。
ただし、こうした税務に関する判断は、行政書士の業務範囲を超える部分も含まれるため、必要に応じて税理士などの専門家と連携を図ることが重要です。
家族信託は、法務・税務・実務の知識が交差する制度です。
そのため、当事務所では内容やご希望に応じて、他士業と連携しながら、依頼者様の目的が正しく反映された契約となるよう支援いたします。
金融機関によっては非対応の場合もある
家族信託を行う際には、受託者名義の「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」を開設するのが理想的ですが、この信託口口座はどの銀行でも対応しているわけではありません。
現時点では、一部の金融機関では制度上対応していなかったり、支店によって取扱いに差があったりするケースがあります。
そのため、せっかく信託契約を作成しても、信託財産となる預金の管理方法に苦慮することがあります。
また、通常の個人口座や法人口座とは異なる手続きが必要となるため、口座開設には時間がかかることもあります。
信託を利用する際は、事前に信託口口座に対応している金融機関を調べておくことが重要です。
不動産の信託登記に登録免許税がかかる
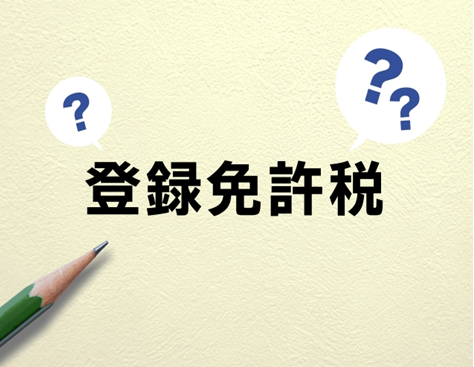
家族信託で不動産を信託財産とする場合、名義を受託者に変更する「信託登記」が必要です。
この登記を行う際には、登録免許税という税金がかかります。
具体的には、不動産の固定資産評価額に対して原則0.4%(※2025年現在)の登録免許税が課税されます。
たとえば、固定資産評価額が2,000万円の土地を信託する場合には、8万円程度の登録免許税が必要になる計算です。
また、登記手続きそのものにも司法書士への報酬がかかるため、初期費用としてある程度まとまった金額が必要となる点に注意が必要です。
信託設計を行う際には、このような費用面も含めて、あらかじめ資金計画を立てておくことが大切です。
※登録免許税は税務に関わる事項のため、詳細な税額の計算や節税の可否などについては、司法書士・税理士等の専門家の関与が必要となります。
行政書士が行う信託スキームのご提案では、登記・税務に関する具体的な業務は対象外となる場合があります。
必要に応じて他士業と連携しながら対応いたします。
税務上の扱いに注意が必要
家族信託は法律上の仕組みであり、贈与や相続とは異なる独自の枠組みですが、税務上はケースによって贈与税・相続税・所得税などの課税対象となる可能性があります。
たとえば、受益者を変更する場合や信託を終了させる場合には、受益権の移転とみなされ、課税関係が生じることがあります。
また、信託財産から得られる収益についても、受益者に課税されることが多いため、信託スキームの設計によっては想定外の税負担が発生することがあります。
そのため、家族信託を検討する際には、税務の専門家(税理士)と連携しながら慎重に設計を進めることが重要です。
※当事務所では、行政書士の業務範囲の中で、信託スキームのご提案や書類作成等をサポートしておりますが、税額の計算や課税可否の判断といった税務判断を伴うご相談については、税理士などの適切な専門家をご紹介・連携のうえ対応させていただきます。
行政書士ができるサポートとは?

ここでは、行政書士ができるサポートについて、解説をしたいと思います。
家族構成や財産内容に応じた最適な設計
行政書士は、単なる「テンプレート契約書」を作成するだけではありません。
ご家族の構成や財産の種類・名義、相続の意向、認知症などのリスクまで丁寧にヒアリングをして、依頼者様それぞれの状況に合わせたオーダーメイドの家族信託設計をご提案します。
たとえば、以下のような事情を考慮しながら、信託スキームを具体化していきます:
- ご家族の構成(配偶者・子・兄弟姉妹などの関係性、同居・別居の有無)
- 相続人間の関係性や過去のトラブルの有無
- 現在の財産の種類(不動産・預貯金・有価証券など)や所有者の名義確認
- 財産を管理・承継したい目的(認知症対策・障がいのある子への備え・遺留分対策など)
- 将来の相続発生時や二次相続を見据えた受益者の設定
これらを踏まえ、無理のない形でスムーズに財産管理・承継ができるよう、信託契約の内容(委託者・受託者・受益者の設定、信託財産の範囲、信託の終了条件など)を一つひとつご相談しながら組み立てていきます。
もちろん「うちのケースでも家族信託は可能なのか?」という段階からでもお気軽にご相談いただけます。
金融機関・登記手続きにも対応
家族信託では、契約書の作成だけでなく、信託用の口座開設や不動産を信託財産とする際の登記対応など、実務面の手続きも欠かせません。
当事務所では、以下のような実務支援も行っています:
信託口口座の開設支援
信託契約書の内容や金融機関ごとの要件を踏まえて、必要書類の準備や申請のサポートを行い、スムーズな口座開設を目指します。
登記手続きに関するサポート(司法書士と連携)
不動産を信託財産とする場合には、法務局での登記申請が必要です。
登記申請は司法書士の専門業務となるため、当事務所では信頼できる司法書士と連携し、申請手続きが円滑に進むよう調整・サポートいたします。
また、お客様ご自身で登記申請される場合には、必要な添付資料の整備や一般的な手続きの流れについてアドバイスすることも可能です。
他士業との連携
信託の実行にあたり、税務や法務などの分野で専門的判断が必要な場合には、必要に応じて税理士や司法書士等の専門家をご紹介し、適切な連携のもとで対応いたします。
家族間の意思調整の支援

家族信託は、ご本人だけでなく、ご家族の理解と協力があってこそ実現できる制度です。
しかしながら、「家族にどう説明すればよいかわからない」「親や兄弟にうまく話ができない」といった声も多く聞かれます。
当事務所では、行政書士として中立・公正な立場から制度の仕組みや必要性を丁寧にご説明し、信託への理解と納得が得られるようサポートいたします。
- 家族信託のメリット・デメリットを客観的に説明してほしい
- 配偶者や子どもにも制度の趣旨を理解してもらいたい
- 親族で話し合いの場を持ちたいが、専門家の立ち会いがあると安心できる
といったご相談に対して、あくまで「説明・助言の提供」という形で関与します。
なお、家族間で意見が対立している場合や、すでに紛争状態にあるような場合は、弁護士による対応が必要となることがあります。
そのような場合には、適切な専門家をご紹介するなど、スムーズな対応ができるよう配慮いたします。
こんな方におすすめです

- 親が高齢になってきて、そろそろ財産管理が心配
- ひとり暮らしの親に不動産があり、将来的に空き家になりそう
- 親が再婚しており、相続関係が複雑
- 家族間での相続トラブルを避けたい
- 将来の認知症に備えて、元気なうちに準備しておきたい
まずは無料相談から、安心の第一歩を
家族信託は、早めの準備が何よりも大切です。
「いつか相談しよう」と思っているうちに、タイミングを逃してしまう方も多くいらっしゃいます。
また、不安を抱えて過ごすのは辛いものです。
話をするだけでも気持ちが楽になったり、整理がついたりすることもありますので、まずはお気軽にご相談ください。